
ゲンバーズは建設業・運送業など現場で働く人を応援する求人サイトです。
RPAとDXが変える建設業の未来:現場・事務・経営に広がるデジタル革命

ゲンバーズは建設業・運送業など現場で働く人を応援する求人サイトです。
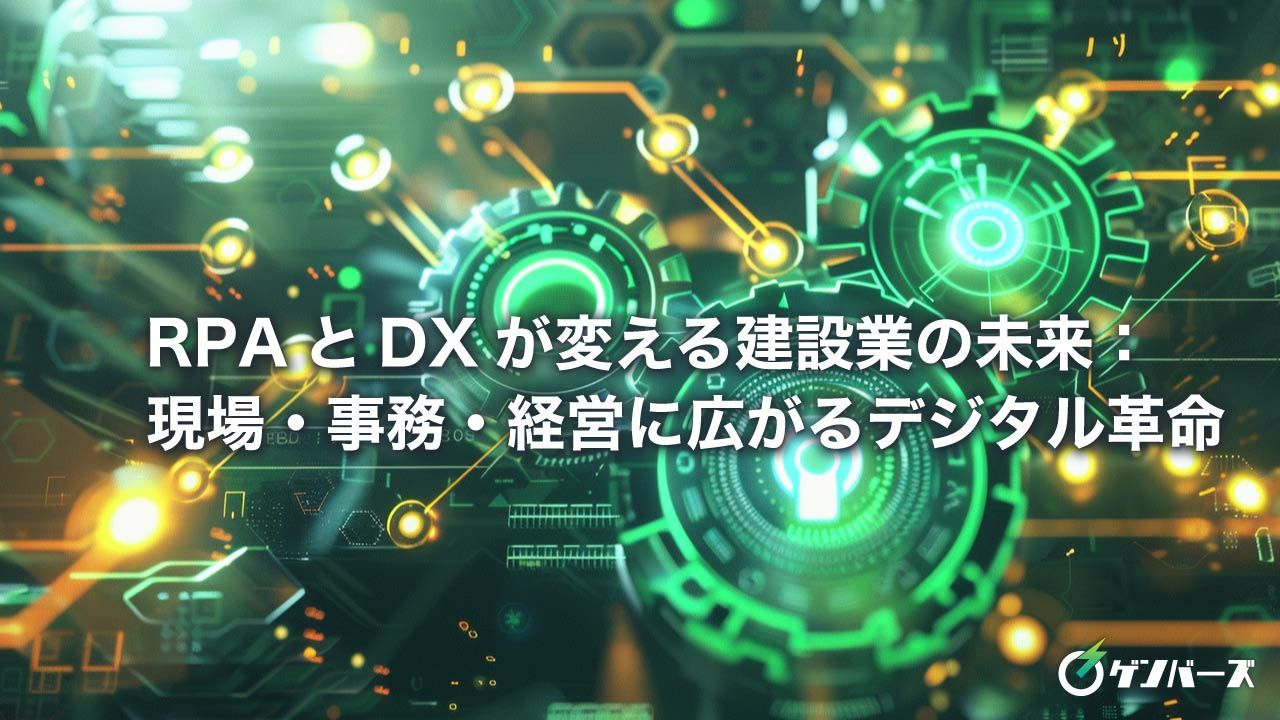
建設業界は長らく「人手不足」「長時間労働」「生産性の低さ」といった課題を抱えてきました。しかし近年、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、これらの問題に抜本的な解決策が見え始めています。現場のデジタル化、バックオフィス業務の自動化、そして経営判断におけるデータ活用は、もはや一部の大手企業だけでなく中小企業にも広がりつつあります。
本記事では現場・事務・経営の3つの視点から、RPAとDXがもたらす変化とその可能性をわかりやすく解説します。未来の建設業における仕事のあり方を一緒に考えてみましょう。
建設業界では慢性的な人手不足や高齢化、長時間労働などの構造的な課題が続いています。その一方で、国や大手ゼネコンを中心にDX推進の動きが加速しており、現場から経営まで幅広くデジタル化の必要性が高まっています。DXは単なる業務効率化にとどまらず、
・安全性の向上働き方改革
・持続可能な経営
の実現に直結する取り組みです。ここでは、その背景やトレンドを整理していきましょう。
DX(Digital Transformation):
単に紙の書類をデジタル化することや、新しいソフトを導入することだけを指す言葉ではありません。本質的には、デジタル技術を活用して、働き方やビジネスの仕組みそのものを変革し、より良い価値を生み出すこと」です。例えば建設業では、設計から施工、管理、維持に至るまでのプロセスをデータでつなぎ、リアルタイムに情報を共有できる仕組みを整えることがDXの一歩です。これにより、無駄な作業を減らし、安全性を高め、働きやすい環境を作ることが可能になります。
建設業は他産業と比べて労働集約型の色合いが強く、長年にわたり人材確保が大きな課題となっています。加えて現場従事者の高齢化が進み、若手人材の確保が難しくなる中、従来のやり方だけでは事業を持続できなくなりつつあります。こうした状況を打破する手段として注目されているのがDXです。デジタル技術の導入によって省力化・効率化を図ることで、少ない人数でも高品質な施工を実現し、若手人材にとっても魅力的な労働環境を整えることが可能となります。
国土交通省は、i-Constructionをはじめとする建設DX推進施策を打ち出し、BIM/CIM(建築・土木の3次元モデル活用)やクラウド技術の普及を積極的に支援しています。これにより、測量や設計、施工、維持管理といった各プロセスでのデジタルデータ活用が進み、従来の紙ベース中心の業務から脱却する流れが加速しています。また、大手ゼネコンだけでなく中小企業にも補助金や助成金を活用した導入事例が広がりつつあり、建設現場 DXが具体的な変化として感じられる段階に入っています。
製造業や物流業ではすでにIoTやAIを活用した自動化・効率化が進んでおり、建設業はそれらと比べるとDX導入のスピードで後れを取っているのが現状です。その要因として、
・プロジェクトごとに条件が異なる現場特性
・紙文化に根付いた業務習慣
が挙げられます。しかし逆に言えば、まだ伸びしろが大きいとも言えます。課題を克服しつつDXを進めることで、生産性の向上や新たなビジネスモデルの創出につながり、業界全体の競争力強化が期待されます。
建設業では、現場が中心と思われがちですが、実際には見積書の作成や請求処理、勤怠管理といった事務作業が膨大に存在します。こうしたバックオフィス業務は手作業の割合が大きく、入力ミスや残業増加の原因にもなっています。そこで注目されているのがRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)です。RPAはパソコン上で繰り返される定型業務を自動化し、人的リソースをより付加価値の高い業務へと振り向けることを可能にします。
従業員の出勤・退勤データを手作業で集計すると、どうしても入力ミスや確認作業が増えます。RPAを導入すれば、勤怠システムと給与計算ソフトを自動連携し、正確な集計が可能になります。同様に、請求書や見積書の作成でも、RPAが指定フォーマットにデータを転記し自動生成してくれるため、人的作業は最終チェックのみで済みます。これにより事務効率が大幅に向上し、ヒューマンエラーの削減につながります。
建設業では発注書や契約書など、紙やPDFの書類が膨大に発生します。RPAはOCR(文字認識)と組み合わせることで、紙やスキャンデータから必要な情報を読み取り、Excelや基幹システムへ自動入力できます。これにより、従来なら数時間かかっていた単純入力作業を数分で終えられるようになります。特に人手不足に悩む中小企業にとって、限られたスタッフでも多くの業務を処理できるようになるのは大きなメリットです。
RPAの導入は単なる効率化にとどまらず、人材不足の解消にもつながります。従来は人を増やして対応していた事務処理をロボットに任せることで、既存スタッフの残業を削減し、より戦略的な業務に時間を使えるようになります。また、働きやすい環境が整うことで離職率の低下にも寄与し、長期的な人材確保にもプラスに働きます。特に女性スタッフや子育て世代にとって、残業が減ることは大きな安心材料となります。
RPAは大企業向けというイメージを持つ方も多いですが、最近では中小企業でも導入しやすい安価なクラウド型サービスが増えています。例えば、クラウド会計ソフトと連携した自動入力や、メール添付された請求書を自動仕分けする仕組みなどは、初期費用を抑えて始められます。また、ノーコード型のRPAツールであれば、IT専門人材がいなくても現場スタッフ自身が簡単な業務フローを作成できます。小規模から試し、効果を実感しながら段階的に拡大していくのが現実的です。
RPA導入を成功させるには「いきなり全部自動化しようとしない」ことが大切です。まずは社内に存在する定例作業を洗い出し、自動化できるものとできないものを区別します。さらに自動化可能な業務の中でも、処理量が多く負担の大きい業務から優先的に選定すると効果を実感しやすいでしょう。すべてをフル自動化するのが難しい業務については、半自動化(データ入力はRPA、最終承認は人間など)の形で取り入れるのも現実的です。最初は小規模に始めて成功体験を積み重ね、徐々に対象範囲を広げていくことが、失敗を防ぎスムーズに定着させるポイントです。
これまで建設現場では、現場での情報と、事務所や本社での管理が分断されがちでした。しかしクラウド技術の普及により、現場とオフィスがシームレスにつながる環境が整いつつあります。施工状況や作業記録をクラウドで共有することで、遠隔地からでも進捗確認や意思決定が可能になり、全体のスピードと精度が向上します。ここでは現場DXの具体的な要素を見ていきましょう。
BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)は、建物や土木構造物を3Dモデルで管理する仕組みです。これをクラウドで共有すれば、設計段階から施工、維持管理まで一貫して同じ情報を関係者全員が確認できます。従来は図面や紙資料を持ち寄って確認していた打ち合わせも、3Dモデルを見ながらオンラインで検討でき、修正や合意形成がスピーディーになります。結果として、手戻りの削減やコストダウンが実現します。
近年は現場にタブレット端末を持ち込むケースが増えています。施工図や作業手順を紙で持ち歩く必要がなくなり、必要な情報をその場で確認可能です。さらに、写真撮影と同時にクラウドへアップロードすれば、事務所や本社がリアルタイムで状況を把握できます。これにより「確認のために事務所へ戻る時間」が不要となり、作業効率が大幅に向上します。若手職人にとってもデジタル端末を使いこなすことは自然なスキルとなりつつあります。
建設現場では、重機や資材の動き、作業員の安全管理など、さまざまなデータをIoTセンサーで取得できるようになっています。例えば、作業員の位置情報を把握することで安全確認を強化したり、重機の稼働状況をモニタリングして効率的な稼働計画を立てたりすることが可能です。こうしたデータはクラウドに集約され、リアルタイムで進捗状況を確認できるため、現場監督や経営者が迅速に判断できる環境が整います。
現場で働く作業員にとってDXは難しい仕組みではなく、日々の仕事を楽にするツールです。例えば、タブレットで施工手順を確認できれば、指示を聞き間違えるリスクが減ります。作業報告も写真や音声入力で済むため、書類作成の負担が軽減します。また、センサーによる安全管理は見守られている安心感につながり、事故防止だけでなく心理的なサポートにもなります。このように、現場のDXは働きやすさと安全性を両立させる重要な要素になっています。
建設DXは現場や事務だけでなく、経営全体の在り方を大きく変える力を持っています。単なる効率化にとどまらず、コスト構造の改善や新たな収益機会の創出、さらには企業競争力の強化に直結する取り組みです。一方で、導入コストや教育体制の整備など、中小企業にとって無視できない課題も存在します。ここでは、経営視点から見たDXのメリットと課題を整理します。
DXの導入により、紙資料や二重入力といった非効率な業務が削減されます。例えば、クラウド管理による進捗共有で手戻りを減らせば、材料費や人件費の無駄を抑制できます。また、RPAによる事務作業の自動化は間接コストを削減し、利益率改善に直結します。短期的には導入コストが発生しますが、中長期的には「ミスや残業の減少=利益の確保」となるため、投資対効果は十分に見込めます。
DXによって現場やバックオフィスから集まるデータをクラウドに統合することで、経営判断の精度が向上します。例えば、工事ごとの収支状況をリアルタイムに把握すれば、赤字プロジェクトを早期に修正でき、経営リスクを最小化できます。また、施工進捗や労務管理データを活用することで、将来の人員配置や資材調達の戦略を練ることが可能になります。データドリブン経営は、今後の建設業界における生き残りの鍵となるでしょう。
一方でDXには導入初期のコストや人材教育の負担が伴います。新しいシステムやツールを入れても、現場や事務スタッフが使いこなせなければ逆に効率が下がる恐れもあります。そのため、導入時には、
・まず小さく始める
・現場の声を取り入れる
・段階的に拡大する
といった工夫が必要です。また、教育コストを抑えるために、直感的に操作できるツールを選ぶこともポイントになります。さらに、DX化が進んだ企業は現場や事務の負担が軽減されるため、働きやすい職場というイメージを求職者にアピールできる効果もあります。これは人材不足が深刻な建設業において、採用力を高める重要な要素となります。
大手ゼネコンでは既にBIM/CIMやIoT、AIを活用した大規模DXが進んでいますが、中小企業では、人材不足、コスト負担の壁が導入を遅らせる要因となっています。しかし近年はクラウド型やサブスク型のシステムが普及し、中小企業でも導入しやすい環境が整いつつあります。大手の事例を参考にしながら、自社の規模やニーズに合わせて現実的なDXを進めることが、持続可能な経営につながります。
これまで建設現場の職人に求められてきたのは、体力や経験をもとにした作業スキルでした。しかしDXの進展により、今後はタブレットやクラウドシステムを自然に使いこなせる力も重要になります。施工図をデジタルで確認し、進捗をアプリに入力することは日常の一部となりつつあります。さらにIoT機器やセンサーを利用して安全情報を把握する場面も増えています。デジタルを活用できる職人は、作業ができるだけの人材からデータを扱える専門職人へと進化し、現場から高い評価を得られるようになるでしょう。
RPAやクラウドツールの普及により、事務業務の多くは自動化されつつあります。単に書類を作成したりデータを入力するだけではなく、今後は自動化された仕組みを正しく理解し、改善につなげられる力が不可欠になります。例えば、RPAの処理フローを自ら調整したり、クラウドに蓄積されたデータを分析して業務効率化に役立てることです。こうしたスキルを持つスタッフは、組織の中で頼られる存在となり、単なる事務員から業務改善のキーパーソンへと成長できます。
DXを進める上で重要なのは、現場と経営の橋渡しを担うリーダー層です。新しいシステムやツールを導入しても、現場が抵抗感を持てば定着は難しくなります。リーダーは現場の不安を汲み取り、使いやすいルールを整え、教育を行う役割を担います。また、経営層に対しては、収集したデータを整理して経営判断に活かせるよう橋渡しすることが求められます。つまりリーダー層は、DXを推進する旗振り役であると同時に、現場の伴走者としても大きな存在感を持つのです。
2030年を見据えた建設業界では、AIやロボット施工、さらに高度なクラウド管理が一般化していくと予測されます。そのとき求められるのはデジタル技術を理解し、使いこなせる人材です。今から少しずつITスキルを磨くことで、将来の安定した働き方につながります。例えば、BIM/CIMやRPAの基礎知識を学んだり、オンライン学習でデータ活用のスキルを身につけたりすることは大きな武器になります。計画的にスキルを強化することで、未来の建設業でも必要とされる存在であり続けられるでしょう。