
ゲンバーズは建設業・運送業など現場で働く人を応援する求人サイトです。
建設業許可の基礎知識と取得のメリットを徹底解説

ゲンバーズは建設業・運送業など現場で働く人を応援する求人サイトです。
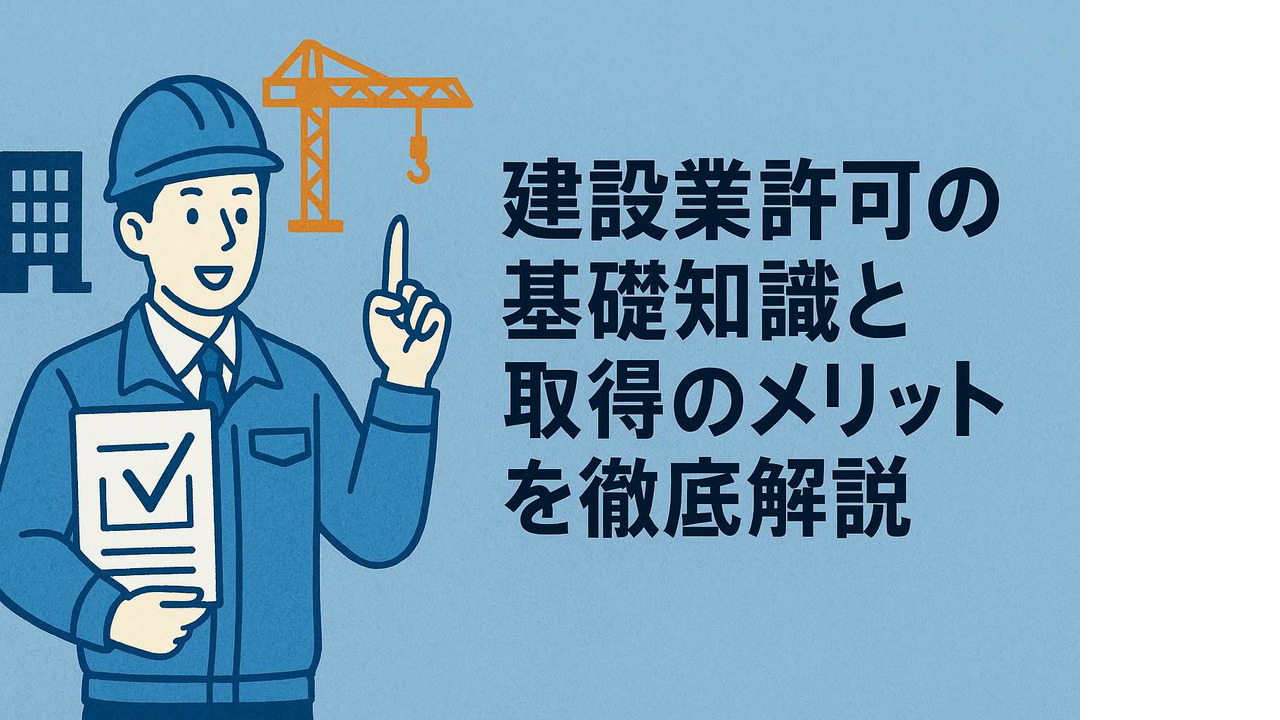
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を行う場合に必要となる国の制度です。許可を取得することで、公共工事の受注が可能になるほか、取引先からの信用度が向上し、融資や資金調達にも好影響を与えます。反対に、許可がないと請け負える工事が制限される場合があるため、建設業においては非常に重要な制度と言えるでしょう。本記事では、建設業許可の基本情報、取得の要件、許可取得のメリット、手続きの流れ、取得後の管理業務までを網羅的に解説します。これから許可取得を目指す方や、取得後の管理を考えている方に役立つ実践的な内容を提供します。
建設業許可は、法律に基づいて規定されている制度で、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要です。許可を取得することで、安全性・信頼性・社会的信用力が大きく向上します。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要な国の認可制度です。この許可を取得することで、法的に認められた建設業者として活動でき、信頼性や安全性が向上します。また、許可の有無は取引先や発注者からの評価にも影響を与える重要な要素です。
建設業許可が必要となるのは、工事1件の請負金額が500万円以上の場合(建築一式工事は1,500万円以上)です。これらの基準を超える工事を行うには、許可を取得しなければなりません。許可がない場合、これらの工事を請け負うことは法律で禁止されています。
建設業許可には、営業所の所在地に応じて「知事許可」と「大臣許可」があります。また、工事の内容により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。自社の事業形態や工事の規模に応じて、適切な許可を選択することが重要です。
建設業許可がないと、一定規模以上の工事を請け負うことができません。また、公共工事の入札や外国人技能実習生の受け入れなども制限されます。無許可で工事を行った場合、法的な罰則を受ける可能性があります。
建設業許可を取得することで、企業の信頼性や社会的信用が向上します。取引先や金融機関からの評価が高まり、ビジネスチャンスの拡大や資金調達の面でも有利になります。許可の取得は、企業の成長にとって重要なステップです。
建設業許可取得には、経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格事由がないことという5つの条件をクリアする必要があります。これらは、企業の経営健全性や技術力を示す大切な基準です。
建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者を設置する必要があります。この責任者は、建設業に関する経営経験を有し、会社の経営を適切に行う能力が求められます。具体的には、一定期間以上の経営経験が必要とされます。
各営業所には、専任技術者を配置する必要があります。専任技術者は、建設工事に関する専門的な知識や技術を有し、工事の品質や安全性を確保する役割を担います。資格や実務経験に基づいて、その能力が評価されます。
建設業許可を取得するには、一定の財産的基礎を有していることが求められます。具体的には、資本金や自己資本が一定額以上であることが必要です。これは、工事の遂行に必要な資金力を持っていることを示すためです。
申請者やその関係者が、過去に不正行為や法令違反を行っていないことが求められます。誠実性の確認は、建設業界の健全な発展と発注者の保護を目的としています。過去の経歴や行動が審査の対象となります。
建設業許可を取得するには、申請者やその関係者が欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件には、破産者や一定の犯罪歴がある者などが含まれます。これらに該当する場合、許可の取得は認められません。
許可を取得することで、公共工事への参入、取引先からの信頼度アップ、金融機関からの融資審査で有利になるなど、多くのメリットがあります。企業価値や営業力の強化につながります。
建設業許可を取得することで、公共工事の入札に参加する資格を得られます。公共工事は安定した受注が見込めるため、企業の経営基盤を強化する上で大きなメリットとなります。
許可を取得していることは、企業の信頼性を示す重要な指標です。取引先や顧客からの評価が高まり、ビジネスチャンスの拡大や新規取引の獲得につながります。
建設業許可を取得している企業は、金融機関からの信頼性が高まり、融資や資金調達の際に有利になります。許可の有無は、事業の安定性や将来性を判断する重要な要素とされ、資金繰りの改善や事業拡大のチャンスを広げます。
許可を持つ企業は、法令遵守や安定した経営体制が整っていると評価され、求職者からの信頼を得やすくなります。これにより、優秀な人材の採用や定着率の向上が期待でき、組織の強化につながります。
建設業許可を取得することで、企業の社会的信用が高まり、ブランド力の向上につながります。許可を持つことは、法令遵守や品質管理の体制が整っている証として、顧客や取引先からの信頼を得る要因となります。
建設業許可の取得手続きは、準備→必要書類の収集・作成→申請→審査→許可証の交付という流れで進行します。特に事前準備がスムーズな申請の鍵となります。
建設業許可の取得には、まず自社の状況を把握し、必要な要件を満たしているか確認することが重要です。経営業務管理責任者や専任技術者の要件、財産的基礎など、各項目をチェックし、必要な資料を準備しましょう。
申請には多くの書類が必要となります。例えば、法人の場合は登記簿謄本や定款、個人事業主の場合は確定申告書などが求められます。これらの書類を正確に収集・作成することで、スムーズな申請が可能となります。
必要書類を整えたら、管轄の行政庁に申請書を提出します。提出後は、書類の内容や要件の適合性について審査が行われます。審査期間は地域や状況によりますが、数週間から数ヶ月かかることがあります。
審査を通過すると、建設業許可証が交付されます。許可証を受け取ったら、営業所や工事現場に標識を掲示する義務があります。この標識は、許可業者であることを示す重要な情報源となります。
許可取得後は、帳簿の整備や契約書の見直しなど、業務体制の整備が求められます。また、定期的な報告や届出の準備を行い、法令遵守の体制を構築することが、事業の安定運営につながります。
建設業許可の有効期間は5年間で、期間が経過すると更新しなければなりません。 更新出来ないと仕事の規模を縮小することになるので、経営的に打撃を受ける可能性がありますので、許可中の義務履行と要件の維持を意識して動く必要があります
建設業許可取得後、商号や代表者、営業所の所在地などに変更があった場合は、一定期間内に変更届出を提出する義務があります。これを怠ると、行政処分の対象となる可能性があるため、速やかな対応が求められます。
毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要があります。この届出には、財務諸表や工事経歴書などが含まれ、経営事項審査を受ける際の基礎資料となります。適切な財務管理と正確な書類作成が求められます。
建設業許可の維持には、経営業務管理責任者(経管)の常勤配置が必要です。経管が退任や退職した場合、速やかに要件を満たす後任を確保しなければ、許可の継続が困難になります。経管の要件には、建設業に関する5年以上の経営経験などが含まれます。
専任技術者の配置は、建設業許可の要件の一つです。技術者が退職した場合や新たに採用する際は、速やかに対応し、必要な資格や経験を有する人材を確保することが重要です。技術者の継続的な育成も求められます。
建設業法や関連法令を遵守することは、許可の維持に不可欠です。不正行為や法令違反が発覚した場合、許可の取消しや営業停止などの厳しい処分を受ける可能性があります。日々の業務において、法令遵守の意識を高めることが重要です。